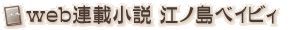 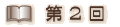
 |
Page [ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ] |
 |

そして今。
どういうわけかボクは、目の前を自転車に乗ったまま回転しながら階段落ちしてきた彼女とケンカしている。
「いちいちウルサいんだよ、このウスラバカ」
と、凄まじい形相で砂浜に向かって叫んでいるのはボクだった。叫びながら、護岸の上の歩道を歩いて行く。バカとか汚い言葉を使ってしまっているのは、結局はボクもあの父の子だとうことで、蛙の子は蛙ってことだ。そう考えるとなんだか嫌な感じなので「死ね」だけは言わないようにしようと自分を戒めた。
「ウ、ウ、ウスラバカァ? 誰がウスラバカよ。ていうかそれ一体いつの時代の言葉よ。もう、そういうこと言うなら、もう、ほんっとに絶対キミのせいだから」
と、まくしたてながら自転車の運転手だった彼女が砂浜からボクを追ってくる。
つまり、ボクと彼女との間には数メートルの護岸の分だけの高低差があり、ボクは左下を見下げて、彼女は右上を見上げて、ふたりで大声でののしり合いながら歩いているという構図だ。行く手にはドリルの塔が突き刺さっている島がある。ボクの歩く歩道の右は車道で、時折、車が行き来している。彼女は自転車を落下地点に置いて来ている。鍵はかけたようだけれど盗られたりしないかな、と敵ながら少し、ほんの少しだけ心のどこかで心配もしてやっている。
先につっかってきたのは、彼女の方だ。
目の前を縦回転する自転車が右から左へとよぎって行き、あまりにもありえない出来事にしばし呆然とした後、おそるおそるその落下地点と思しき場所の方へと目を向けると、ボクの目に映ったのは砂の上に倒れた誰も乗っていないママチャリだった。一瞬のことだったし誰か乗っていたと思ったのは見間違いだったのかな、とも思ったけれど、すぐに、着地する前に運転手は体よく言えば脱出した、ぶっちゃけて言えば投げ出されたのだと分かった。
自転車から少し離れたところから、裏返った声が上がる。
「危ないわね、もうっ」
声の方へと目を向けると、立ってボクをまっすぐ睨みつけている彼女がいた。制服を着ているから、多分、高校生だろう。中学生にしては、少し大人っぽい。ボクよりは年上だろうと思う。背中まであるさらさらした黒く細い髪と、端正な顔立ち。お嬢様っぽい綺麗系だけれど、押し寄せる波を背景に砂まみれでキレた様子は、とてもではないけれどお嬢様とは言えない。元々は色白なのだろう。興奮で血が上った顔は真っ赤だった。
「あ……すみません……」
気圧されて、つい謝ってしまったけれど、よくよく考えればボクはなにも悪くない。大体、たまたま壁際に身を寄せていたからいいようなものの、普通に階段を登っていたら、回転しながら落ちてくる自転車と正面衝突して大けがをしているところで、いっそこっちがキレたいぐらいだ。
「ホントもう、なにやってたのよ、あんなところで」
彼女はキレたまま勝手なことを言っている。
「え……いや、それはこっちが……訊きた……」
ボクは普通に階段を上がろうとしていただけだ。途中で立ち止まって壁際で携帯をチェックしていたりしたけれど、それだって別に非難されるようなことじゃないと思う。それともなんだ? 彼女は自転車でほぼ垂直に近い護岸を駆け下りようとして、そのコース上にボクがいたので仕方なく縦回転しながら転がり落ちて行ったとでも言うのだろうか。そんなことをする理由が分からないが、そうだったと仮定してボクが悪いことになる理由を自分の中で探してみた。
一 実は映画の撮影で、知らない間にボクは入ってはいけない場所にまぎれこんでしまっていた。
二 ……。
二で詰まってしまった。
彼女は砂を落とそうと、やっきになって体中をはたいている。カンフー映画でも観ているようだった。
「あーあー、もう、砂まみれ。これじゃ学校行きたくても行けないじゃない。うわ、ブラの中まで砂入ってるし、あーキモイー」
どうやら映画ではないらしい。

 |
Page [ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ] |
 |
|