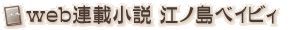 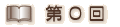
 |
Page [ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ] |
 |

-1 『歩く』
靴の中に砂が入っている。
歩きながら左足の親指と人差し指を上下にこすり合わせると、いくつもの硬く小さな湿った粒が、皮膚と皮膚との表面を削るように転がるのが分かった。
湿っているのが汗のせいなのか潮のせいなのか、良く分からない。足の指だけではなく全身がそうだった。服の下に隠れた肌にまで、ヌルい水蒸気が一様に貼りついている。
波の鳴るのを聞きながら砂を踏む。
ずっと歩いた。濡れた波打ち際は、ひと足蹴る度に固まった砂が沈んだ。波が届かない乾いた砂は蹴る度に粉々に砕けて得体が知れなかった。黒い絶壁と言っていい護岸近くは、その上の車道を照らすオレンジの灯が全く届かない影になり怖かった。
時折、立ち止まりもした。続いていく砂の中へ海に浮かぶ島のように顔を出す平たい岩へ腰を下ろして、本物の海の方へ目を向けた。風か波か、岩の肌は磨り減ってどこか丸みを帯びていた。上に掛かっていた砂は適当に素手で払った。
深く濁った藍色の、遠い場所を見つめていた。不意に盛り上がり沸き立つ波頭の色を白だとは思えない。擦れたデニムの色だ。泡立ちながら沸き起こり、列になり、炭酸飲料のように跳ねて、崩れながら、こちらに向かってこようとする。ただの威嚇かとすら思えるほどに、その速度は異常に遅い。この海には色の遠近感がない。ただ一面の藍。遠くとも近くとも分からない所で、波頭は砕け生まれ、浜へたどり着く前に壊れ、再び浜の近くで大きな列を成し砂を食む。
一、二、三、よん、ご、ろく、なな……。
歩く先に、大きく盛り上がる黒い影が見える。ふもとに近い位置で、横一列に強く光る黄色を集めている。左の端で二秒おきぐらいの間隔で、エメラルド色の発光。右の端には、等間隔に並ぶオレンジ色の光が更に右へと続いていて、これは橋だ。影は島らしい。
……じゅう、じゅういち、じゅうに、十三、十四、十五。
十五歩で、時計周りに光が一周してきてボクの目を突き刺す。小学校の頃に理科の実験で使った豆電球を強力にしたような光だ。島の頂上に塔が建てられていて灯台になっている、その光だ。
後ろを振り返れば、遠く、海岸線の山沿いに広がる街の灯がある。淡く瞬いて、そっちの方が奇麗だった。
空に星はない。月もない。曇っていた。
誰もいない砂の上をボクは歩き続ける。
波の音は、バチバチと、かなりうるさい。何もかもをかき消して、ほとんどそれだけでボクの頭の中を埋め尽くすのを気に入っていた。
車かまだ何台も走っていた時間から、ずっと、コンクリートの絶壁である護岸の上からの音なんて、ほとんど聞こえない。
この砂浜には他には誰もいない。ボクだけだ。
キラー・ビーチ。
久しぶりの爽やかな気分で、ボクは歌った。
明るく大声で歌いながら、夜明けの遠い六月の浜辺を歩いた。

 |
Page [ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ] |
 |
|