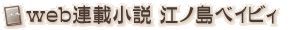 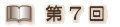
 |
Page [ 1
・ 2 ・ 3 ] |
 |

家のある江古田から電車に乗って三つ行った駅から十五分ほど歩いた場所に、ボクたちの高校はある。駅からは、多数の同じ学校の制服に身を包んだ人たちが、同じ方向へ向かって進んでいる。流れに身を任せて進めばいいので迷う事はなさそうだ。その流れの中に見慣れた黒髪を見つけて、ボクは「はっ、ほっ」とか息を声に出しながら華麗なステップで人波を縫い、近寄って行く。
「ういっす、美樹」
追いついた黒髪の子の肩を叩いた。
首まで緩やかなカーブを描くその髪を振り乱して、美樹が勢い良く振り向く。
「葉月ー。おはよー。元気だったー?」
ボクの両肩に手を置いて何度も飛び跳ねながら、美樹は少しだらしないような笑顔を広げる。幼い動作が新品の格式張ったジャケットに似合っていない。
美樹はボクと同じ中学出身だ。ボクの親友だった。
「ホント、ひさしぶり」
「ヘイヘイ、三日ぶりぐらいじゃねーかー?」
ボクシングの真似をして美樹はボクのお腹にジャブを入れる。苦痛のフリをして「うっ」とか言って顔を歪めてみせた。
親友というのもボクたちレベルの仲の良さまで来てしまうと、一緒に待ち合わせての登校とかはしなくなる。今朝も、メールのやりとりはしていたけれど、駅で待ち合わせで一緒に電車に乗ろうとか、そんな話にはならなかった。
「三日間、元気してた?」
ボクが訊くと、美樹はまた前を向いた。片手でボクの二の腕を叩き、先に進もうと言葉に出さずに促した。二人、並んで歩き出す。
「なんもなかったよ」
自嘲気味に、そう言う。
「それは何よりだ」
美樹はエラく頭がいい。血みどろの自虐的な努力の末にようやく合格したボクとは違って、受験ではあんまり苦労はしなかった。本当はしていたのかもしれないけれど、傍目のボクから見ていると、なんの苦労もしていなかったようにしか見えない。シャーペン振り回して口笛吹きながら問題集の空欄を埋めて行く美樹に、正直、『コノヤロウ』と思ったりもしたけれど、それは人並みの正当な嫉妬だろう。
「ずっとインターネットしてた」
「はァ?」
眉根を寄せて聞き返してしまった。すぐに思い当たる。
「……あ、携帯で?」
なんか随分金かかりそうだなぁ、と思いつつも訊いた。ボクの携帯は、親の、電話代使いすぎないようにとの配慮からプリペイドだ。殆どのやりとりがメールだから、それでも充分に事足りている。長電話なら、家電を使えばいい。
「いや」
こともなげに否定する美樹。
「パソコン買ったとか」
「そう。そうそうそうー」
大はしゃぎでヘッドバンギングの美樹。ボクは素直に驚いておく。
「へー」
「ま、私専用のでなくって、家のだけど」
「なんだ」
「いやーでも、結構楽しいよー。家にいながらにしていろんな情報が手に入ってさー。どーでもいーよーな情報もあるけど」
「でも、美樹のことだしなー。すぐ飽きそー」
「かもしんない。なんかやった後、時間無駄にしたなーとか思わなくもないし。……ああ、そんでね?」
美樹がポケットから定期入れを出す。白っぽい茶色の革の定期入れだった。春休み中に一緒に映画観に行った時は持ってなかったから、学校用の新品なのだろう。美樹はそこからピンクの紙切れを取り出して、ボクに渡す。
「それ、私のパソコンのメルアド」
「お、おう」
付箋紙だった。人差し指ぐらいの長さの短冊に、シャーペンでアドレスが書かれている。
「……携帯に送れば良かったのに」
「え? 送れんの? バソコンから携帯って」
目を見開いて美樹がボクに訊いた。
「多分……」
としかボクには答えようがない。ボクはiPod使ってるしパソコンも持っていて、ネットも多少はやるけれど、メールのやりとりは100%、携帯で行っている。パソコンからメールを送ってくるような人が周りにいないし、パソコンでメールを送る必要が出来たこともない。時々、何かの拍子で勝手にメールソフトが立ち上がるけど、ウっザいなぁ、とボヤキつつバッテン印を押して消している。
「んっじゃぁ、葉月に宿題」
美樹が言う。
「はい。なんでしょ」
「後で、葉月のパソコンから私の携帯にメール送ってよ。届くかどうか確認するから」
「自分でやれよ。自分のパソコンから自分の携帯にさ」
意地悪く言ってやった。
「えー。空しいじゃん。届いたのが自分からのメールなんてすっげぇ寂しい人っぽくね? ぜってー、超ヘコむ」
「まぁね」
携帯を出して、メルアドを登録する。歩きながらなので、少し打ちにくい。教室に着いたら、このアドレスになんか送ってやろう、などと思いついた時、
「高田ぁ」
と、美樹が声を上げた。
目を上げると、少し先に新しい制服を着た高田が、ボクたちの方を振り向いて、足を止めていた。高田は男子だ。ボクや美樹とは同じ中学の出身で、先に言っとくと、彼こそがボクが好きな人であり、麗しの高校生活バラ色計画の要でもある。

 |
Page [ 1
・ 2 ・ 3 ] |
 |
|