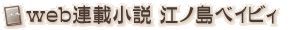 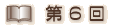
 |
Page [ 1
・ 2 ・ 3 ] |
 |

「……まぁ、何というか家出ですかねー」
間違いではないどころか、真実だ。下手したら警察に突き出されかねない失言だけれど、もうそれでもいいや、とヤケも半分ぐらい入っている。あとの半分は楽観で、この人なら多分、警察呼んだりはしないだろうなぁ、と希望まじりに考えていた。
「へー。若いのに大したモンだ」
みささんは目を丸くする。
「いや、全然……」
軽く右手を振って、笑顔を浮かべて謙遜。
「書を捨てよ、家出しよう。か……」
「なんですか? それ」
「寺山修司っつー……詩人? の本のタイトル。その若さじゃ知らないか」
「すみません……。知らないです」
また、口を閉じたままでみささんが笑った。その声は籠った暖かな音になる。
「私も読んだ事はないんだけどねー」
それきり、また会話が止まった。
しばらくして、みささんはボクから目を逸らして「やれやれ」と口に出したけれど、それが誰に向けての「やれやれ」なのかは良く分からない。
家出してきたボクへ向けての「やれやれ」のような気もするし、いつまで経ってもお風呂場から出て来ない雪野に向けての「やれやれ」のようにも聞こえた。
もしかしたら、ボクのような十も歳の離れた他人と会話が繋げられない自分自身へ向けての「やれやれ」かも知れないけれど、そうだとしても、それはみささんのせいじゃない。
かと言ってボクのせいかとも言うと、そうとも言い切れないと思うし、こういうものはもう仕方がないのだとも思う。
タイミングというか、合う合わないの相性というか、そういうものがやっぱりあるのだ。ある、というだけではなくて、合うと思っていた人が、本当の所では全然合っていなかったり、テニスのダブルスのペアみたいに何をするのでもタイミングがバッチリの最強コンビだと思っていた人との息が、ある日から急にガタガタになって、しまいには何やってもウザげな目で見られるようになったり、そういうのも、ある。
それでも今のこの部屋には、重く湿った悪意が垂れ込めていないから、ボクは幾分、落ち着いていられる。
携帯をポケットから取り出した。
チェックする。
新着のメールも、着信も、やっぱりない。
ボクが待ち続けているメールがいつから来なくなったのか、受信フォルダの一番上に来ているメールの日付を調べれば分かる事だけれど、なんだか怖くてできそうにない。本当は日付も覚えているけれど、意識したくはない。
そんなことを考えている今も、心拍数が少し上がりそうになっている。みささんも前にいることだし、人前で鬱になるのは嫌だなあとも思う。
あんまり思い出したくはない事だ。思い出さなければ、思い出さないに越したことはない。
ドアが開く音がした。
振り向くと、雪野が出ていた。
白と黒のツートンの、可愛らしい服を着ている。
スカートの丈が若干、短い。気がする。その下に、白くて細い脚がすらりと生えている。細くはあるけれど、骨張っている訳ではなく、すね毛の処理も完璧で、形が良い。気がする。キレイ過ぎて逆に自転車で突っ込んだせいらしきアザが痛々しい。
「どうも」
低い声で言った後、雪野はボクたちの座るソファの方へ近づいて来る。
「おー。やっと上がったか」
みささんが、雪野の方へと声を掛ける。
みささんが座っているソファの横に立ったままでいる。
「長くてすみません」
雪野はそう謝って微笑んだ。キレイな笑顔で、シャワールームから出て来た時の上がって来た時の憮然としたように表情からの移り変わりがなめらかだった。
「風呂で溺れ死んでるかと思ったよ」
みささんの言葉に、雪野は眉根を寄せた苦笑で肩をすくめて答える。よく見ると、眉毛もキレイだ。抜いてるとか切ってるとか手入れをちゃんとしているんだろう。
「で、どうすんの?」
みささんが訊く。
「一端、家に帰って、それから学校に行こうと思います」
「ん。それがいいかもね」
「……直接、家に帰っていればシャワー借りる必要ってなかったですね」
すまなさそうな顔で言う雪野に、みささんは軽い調子で
「いいんじゃないの?」
と言った。
そうして、突き出した人差し指をメトロノームの針みたいに左右に揺らしながら
「どーせタダなんだしさぁ、使わにゃソンソン」
とまで言う。
こういういい加減な人が上司だと色々と楽なんだろうなぁ、ボクはふと思う。バイトするなら、こんな店で働きたい、と形だけ思う。勿論、そんな気は全くない。

 |
Page [ 1
・ 2 ・ 3 ] |
 |
|