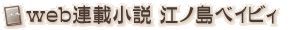 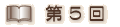
 |
Page [ 1
・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ] |
 |

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
「二階に従業員専用の憩いの部屋があンのよ、変わってるでしょ」
狭い階段の一段目を登りながら、「ん」がカタカナの「ン」っぽく聞こえるような詰まったアクセントで、みささんは言う。特攻服着て改造バイクの前でだらしなく座っている暴走族の発音の感じと言えば、分かり易いかもしれない。
「はぁ……」
階段の登り端から、店内の様子が見えた。洒落た椅子とテーブル、シックな内装。さっきボクが覗いていた小窓の向かいに当たる壁は、ほとんど全面がガラス張りで、その奥にテラス、その先に海、そしてずっと奥に江ノ島が見えた。見た感じは完全にレストランだ。けれど、違和感がある。何かが足りない。
なんだろう、と、みささんの後ろについて階段を登りながら考える。
---そうか!
客席のテーブルの上に何も載っていないのだ。
ここが本当にレストランであるのなら、フォークやナイフの入った籠、メニューの冊子、唐辛子とか塩とかの瓶、そういった『レストランには当然あるべきはずのもの』が、テーブルの上には置かれていなければならないはずだ。それなのに、テーブルには何一つ載っていない。何一つ、だ。
これはつまり、この店はそういった『食事をするための道具』が全く必要とされない場所だと言うことを指し示しており、それは何故かと言うなら、この店で客に振る舞われるのは料理ではなく、女の子だからなのである。挙動不審で妙な笑い声をあげるジジィどもが、その舌でご賞味するのは旬の食材ではなく、まだ青い果実と言うわけだ。
「ここはイタリアンのレストランなんだけどねー」
みささんが言う。
「レストランなんですか?」
目を丸くしたボクが上げた声が大きかったのか、みささんが最後の段で足を止めて振り返る。
「え? なんでよ?」
「あ……いえ……。レストランにしては、フォークとか、メニューとか、ないなぁ、と……」
みささんは笑った。
「開店してないのに置かないよ、そんなの」
……そうなのか。
よく考えてみれば、自宅にだってフォークやナイフをしまう食器棚があるのだし、それはそうか。
階段を登り詰めたみささんが言う。
「山崎さんは飲食店でバイトした経験ないな」
「あ、はい……」
階段を登りきると、そこには真っ直ぐ続く通路があった。
「今、何年?」
歩きながら、みささんが訊く。
あまり訊かれたくない質問だった。
今日は学校休み? と、突っ込まれたら、創立記念日だから、と返そうかと心しつつ
「高一です……一応」
と、答え、みささんの後をついていく。
通路は明るい。左右の壁に、窓ガラスがずっと並んでいて陽光が存分に入って来る。この通路はボクがロリコンっぽい店名の看板を見上げていた建物の外の位置からも見えていた。
通路と平行に並んで、一階の屋上に建て増した感じの、箱のような二階部分がある。何故そう見えるかと言えば、一階の壁とは色が違うからだ。一階のいかにもレストランですという感じの大人っぽい赤茶色の壁とは違い、二階のこの箱の壁は白い。
通路はもっと前の方で右へと直角に曲がり、箱の入り口に繋がっているようだった。上から見ると、通路と二階の箱とで、上の棒がちょっと長いコの字型になっていると思う。ちょっと長い上の棒に当たるのが今歩いている通路で、そのコの字の通路と箱との間に京都との寺とかにありそうな庭がある。白くて丸い石が波紋を描く中に、苔むした松っぽい木がひょろっと捻れ曲がって立っている。横を見つつ、なんでもありだな、と、思ってちょっと笑った。
「高一か……」
みささんはそう言って、ボクは身構えたけれど、次のみささんの質問はボクの予想とは違っていた。
「いいねー、若くて。幾つ?」
そうか、若いのか。
そうだよな、若いんだ。
「十五です」
話の流れで、逆に訊いてみる。
「みささんは……お幾つですか?」
「私? 私は二十五。いやぁ、十も違うんだよなぁ……」
渇いた笑いで角を曲がる。
二十五ならまだまだ若いじゃないですか、と思えるほど、ボクは歳を取っていない。二十でも老けてるなぁと思うのが実際だし、さっきもみささんを見て二十は超えているな、と思ったのは悪意はないけれど無意識的に否定的な意味合いであり、ぶっちゃけた話、まだ若い自分に優越感を感じたからだろうから、今、みささんの言葉の語尾が詠嘆か何かで消えて行ったのは納得できた。
「あ、拓海も十五だな、確か……。雪野は十七ね。で、あいつは高ニ」
曲がった角の先にはドアがあった。
庭と通路からして、もう少し洒落た感じを予想していたのに、普通の家屋の江古田にあるボクの部屋のドアと似たような程度の安っぽい扉だった。鍵はついているらしい。
ドアが開く。鍵が開いていたのは、雪野が先に来ているからだろう。

 |
Page [ 1
・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ] |
 |
|